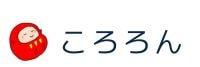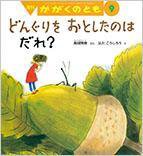どんぐりの中にいる虫はいつ出てくるかというと、翌日だったり、数週間かかって出てくることもあります。
どんな虫なのかというと、主にゾウムシやハイイロチョッキリなどの小さな虫の幼虫です。
家の中で虫が出てこないようにするには、虫処理しましょう。
煮沸や冷凍、塩水につける方法があります。
(茹でるのがおすすめ)
幼稚園などの製作物に使われたり、子供の宝箱にも入っていたりするドングリ。
この記事では、どんぐり虫は何になるのかや危険はないのか、出てこない方法、虫食いの見分け方などをお伝えしていきます。
どんぐりの虫はいつ出てくる?家の中で発生したらどうすればいい?
小さなお子さんがいると、秋にどんぐりを拾う機会も多いのではないでしょうか?
家の中で保管していたドングリから、小さな虫が出てきてびっくり!なんて経験はありませんか?
私も、大騒ぎしたことがあります。
どんぐりの虫がいつ出てくるのかは、実ははっきりした日数はわかりません。
自然に出てくるのですが、1日で出てくる場合や、一週間、中にはそれ以上たってから出てくることも・・・
どんぐりの中の虫は、どんぐりがやわらかい緑色の実の頃に卵が産みつけられます。
そして、どんぐりの中で育ちます。
さなぎになる前の幼虫の姿で、ドングリから出てくるのです。
拾ったどんぐりから虫が出てくるのは、産卵の時期が関係しているので、見ただけでは判断が難しいのです。
実際、私が拾ったどんぐりは、翌日に虫が出てきました。
知人の幼稚園の先生は、箱の中に一週間以上置いて、虫が出てくるのを待っていたそうです。
すると、2、3日で出てくるものもいれば、一週間たってから出てきたのもあったとのことでした。
また、どんぐり一つにつき一つの卵とは限りません。
そのため「虫が出てきたから、もう出てこない!」と考えるのも危険です。
一匹出てきたら、今後も出てくるかも・・・と考えた方がよいかもしれません。
もし、家の中でどんぐりから出た虫がいたら・・・
考えたくないですが、子どもの机や、箱の中で発見されることが多々あります・・・
もし虫が発生してしまったら、なんとか拾い集めるしかないでしょう。
(あとで紹介しますが、小さい虫や蛾の幼虫なので、特に害はありません)
または、掃除機で吸うとか…。
私は、木々が多いところに住んでいたので、どんぐり虫はどんぐりと一緒に拾った場所に返してきました。
袋に入れて、口をしっかり閉めて保管していたので、自然に返すのも簡単で良かったです。
どんぐりを捨てたくない場合は、どんぐり虫を取り除いて、これ以上虫が出てこないように処理をしましょう。
一番は、虫が出てくる前に対処するのがベストです。
拾ってきた際に処理をしていれば、どんぐりから虫が出てくることもなくなりますよ。
どんぐりの処理方法について、詳しくは次の章で紹介します!
どんぐりの虫処理は茹でる?冷凍する?
家の中でどんぐりから虫が出てこないように、ドングリを拾って帰ったら、茹でたり冷凍などをして処理をしましょう。
どんぐりをゆでる(煮沸)
まずは、ゆでて虫処理する方法です。
拾ってきたどんぐりを、熱湯で茹でます。
煮沸する時間は8分~10分ほどがよいでしょう。
その後は新聞紙の上などで陰干しをし、自然乾燥すればOK。
鍋で茹でるのに抵抗がある方におすすめしたいのが、100均で買える小さな鍋です。
私はいつもの鍋で茹でるのは抵抗があったので、100均で購入した小鍋をどんぐり用として使っています。
また、耐熱の袋に入れて茹でるのもおすすめです。
例)Iwatani アイラップ
※アイラップの耐熱温度は120℃です。高温になる鍋底に直接触れないよう、必ずお皿などを敷いてくださいね
どんぐりを冷凍する
次に紹介するのは、冷凍する方法です。
ドングリを袋などに入れて、冷凍庫に3日以上置きます。
しっかり冷凍する必要があるので、冷凍庫の開け閉めが多いところは避けた方がよいでしょう。
その後は、新聞紙などの上で陰干しをし、自然乾燥をします。
不安な方は一週間程、冷凍しておくとよいでしょう。
どんぐりを塩水につける
どんぐりの虫処理には、塩水に浸ける方法もあります。
水500mlに対して塩大さじ1くらいの塩水に、どんぐりを浸けておくというものです。
2、3日つけたら、水を切り、陰干しでの自然乾燥をしましょう。
ちなみに、塩水に浸けた時にすぐ浮いてきたどんぐりは、既に虫食いされたものです。
虫に食べられて、どんぐりの中が空洞になっているんですね。
後ほど、どんぐりに虫がいるかどうかの見分け方をご紹介しますが、水につけてみるというのも見分け方の一つになりますよ。
この他にも、電子レンジで加熱する虫処理のやり方もありますが、破裂する恐れがあるのでおすすめしません。
私は、煮沸が一番手っ取り早いので、ゆでる方法で虫対策しています。
ぜひ皆さんも、自分に合った処理方法を試してみてくださいね。
どんぐり虫って危険?どんな虫で何になる?
どんぐり虫は、主に、落下前のどんぐりに産み付けられた卵から孵化した幼虫です。
どんぐりから虫が出てくると、怖かったり触っていいのか不安になる人もいるかもしれませんが、危険ではないので大丈夫です。
ドングリから虫が出てきたときに、どうやって入ったんだろう…と思うかもしれませんが、中に卵があったんですね。
どんぐりの中にいる虫は、どんぐり虫と呼ばれますが「どんぐり虫」という名前の虫がいるわけではありません。
「ゾウムシ」の仲間や「ハイイロチョッキリ」の幼虫のことが多いです。
- クヌギシギゾウムシ、コナラシギゾウムシなど(ゾウムシ科)
- ハイイロチョッキリ(オトシブミ科)
この他に、落下後のどんぐりにつくハマキガ科の幼虫や、落下したどんぐりに卵を産み付ける、キクイムシ科の幼虫もいるそうです。
クロシギゾウムシ
クヌギシギゾウムシ
エゴシギゾウムシ pic.twitter.com/08w5XTasrF— 橋間仁ΦζΦ折紙魔人(Origami Mazin) (@bmcnh407) May 21, 2022
どんぐり虫が大きくなると何になるかというと、ゾウムシの場合は1cmほどの小さな虫になります。
ゾウムシの成虫は、名前のとおり、象の鼻に似ているのが特徴です(twitter画像参照)。
鼻のような部分は、口吻(こうふん)という器官です。
この、象のようなくちばし?で、ドングリに穴をあけて産卵するんですね。
ゾウムシには、クヌギシギゾウムシ、コナラシギゾウムシ以外にもたくさん種類があります。
ハイイロチョッキリも、象の鼻のような見た目でゾウムシと似ています(私には違いがよくわかりませんでした…)。
ちなみに、ハイイロチョッキリは、産卵後にどんぐりを枝ごと切り落とします。
枝ごと落ちたどんぐりがあれば、ハイイロチョッキリの仕業だと思ってください。
虫がいるであろう「どんぐり」を避けることができるでしょう。
ハイイロチョッキリの参考動画
NHK for School 「どんぐりとハイイロチョッキリ」
どんぐり虫は特に危険ではありません。
ただし、小さなお子さんが口に入れてしまったら大変です!
そうならないためにも、しっかりとドングリ虫処理をしましょう。
大量にどんぐりから虫が出てきたら、それだけで恐ろしく感じる方も多いのでは?
どんぐりを処理せず、箱や引き出しの中に入れておくことが、一番危険かもしれませんね。
どんぐり虫がいるかどうかの見分け方
どんぐり虫がいるかどうかの一番の見分け方は、産卵の跡(穴)があるかないかです。
しかし1ミリ程の小さな穴なので、虫メガネなどで確認する必要があります。
ゾウムシの仲間は、青く柔らかいどんぐりに小さな穴をあけて産卵します。
どんぐりの帽子の近くや、ぼうしの部分に黒い点があれば、ほぼ産卵されたどんぐりと思ってよいでしょう。
また「ハイイロチョッキリ」は、先ほど紹介したように、産卵後に木の枝ごとどんぐりを落とします。
そのため、枝のついたどんぐりには、虫がいると思って避けるとよいでしょう。
休日に散歩中…
「ハイイロチョッキリだー!!」
と、息子が叫んだ。普段は何気なく見過ごしていた景色も
絵本体験をすることで見える世界が変わる。#かがくのとも #福音館#ハイイロチョッキリ pic.twitter.com/mOLvCSSGip— こどものとも東北 (@tomo_tohoku2018) August 24, 2022
他には、どんぐり虫の処理の項目でお伝えしたように、水につけて浮くかどうかの見分け方もあります。
どんぐりに産卵された卵は、どんぐりの中で孵化し、どんぐりを食べて大きくなっていきます。
さなぎになる前にどんぐりから出てくるので、目で確認できる大きさの穴があれば、それは幼虫が食べた虫食いどんぐりです。
また、「どんぐり」にも種類があります。
↓ とてもわかりやすい図と説明を発見!
よく「コナラ」や「クヌギ」には虫が多いと言われています。
もし他の種類のどんぐりが手に入るのなら「コナラ」「クヌギ」を避けるのもよいかもしれません。
(逆に、コナラは虫食いが少ないという情報もありますが。)
ただ、落下後のどんぐりは、「ゾウムシ」以外の虫(ハマキガなど)がいる可能性もあるので、注意は必要です。
見分け方をまとめると、主に次の4つです。
- 穴が開いているどんぐりを避ける
- 枝のついたドングリを避ける
- コナラやクヌギのどんぐりを避ける
- 水につけて浮くどんぐりを避ける
私も、1や2に注意してどんぐりを探していますが、やはり虫が中から出てくることがありました。
どんぐりを持ち帰る際は、必ず処理するのを忘れないことが大事です。
さいごに
わが子が通う幼稚園では、どんぐりを持ってくる際に虫処理をするルールがあります。
そのため、私は見分け方を活用しつつ、どんぐりを煮る処理をしています。
必要以上にはどんぐりを持ち帰らず、その場で楽しんで、自然に返すのが一番楽でよいかもしれませんね。
秋を感じられるどんぐり。
子どもの集めたい気持ちや、作品に残したい、おもちゃとして遊びたい気持ちをくすぐります。
お子さんが「どんぐりを拾いたい!持ち帰りたい!」と言った時は、ぜひ参考にしてみてくださいね。