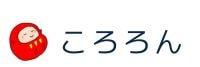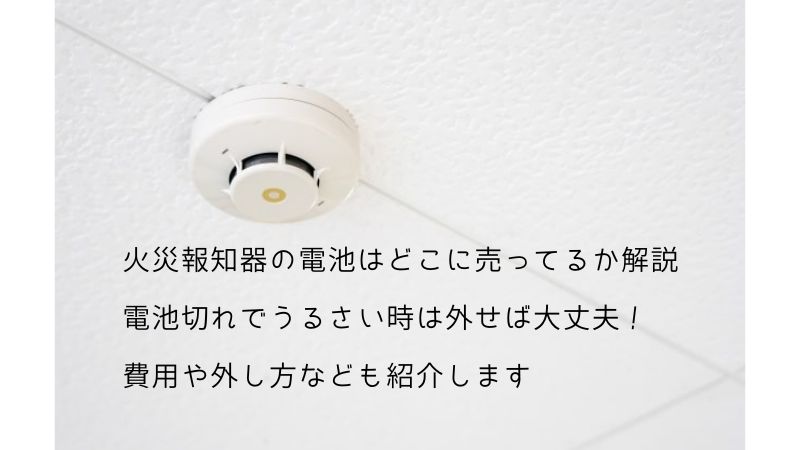この記事では、火災報知器(火災警報器)の交換用電池はどこに売っているのかや交換方法、値段などをご紹介します。
火災報知器の電池は、インターネット通販で売っています。
例)パナソニック SH384552520
電器屋さんやホームセンターではあまり売ってません。
電池切れ音が鳴りやまなくて困った時は、電池を外せば止まります。
電池交換は自分でできて、費用も電池代の1000円ほど。
電池の外し方についても「火災報知器を壁や天井から取り外し、コネクタを引き抜くだけ」といたって簡単です!
このように、住宅用火災報知器は簡単に電池交換できますが、10年を目安に本体交換が推奨されています。
我が家の電池は10年持たなかった気がしますが、電池切れの時は、本体の交換時期かもしれませんね。
火災報知器本体も、もちろん通販で買えますよ。
火災報知器の電池はどこに売ってるのか解説(ケーズデンキやエディオン、コーナンなど)
火災報知器の電池は、ネット通販で購入するのがおすすめです。
普段お使いの電池、例えば単3乾電池は、どこのお店でも購入できますよね。
では、火災報知器の電池を買う場所は?というと、思い浮かぶのはケーズデンキやエディオン、ヤマダ電機といった家電量販店や、コーナンのようなホームセンターだと思います。
確かに今挙げたお店は、どこも火災報知器の本体を扱っています。
でも、交換用の電池まで扱っているお店は、案外少ないんです。
せっかくお店に行ったのに、電池の取り扱いがないのは悲しいですよね。
そんな時は、先ほど述べた通り、インターネット通販を利用しましょう。
ネット通販なら、電池の品番さえわかれば購入できるので、お店で探す手間も省けます。
例えば、パナソニックの火災警報器の交換用電池「SH384552520」。
これをAmazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどで検索すると多数ヒットします。
普段お使いのECサイトで、手軽に購入が可能なのです。
ちなみに、我が家もAmazonで購入しました。
もし急いでいる場合は、お急ぎ便が無料で使える「Amazonプライム会員」が便利だと思います。
ご存じの方も多いと思いますが、Amazonプライムでは30日間の無料体験があるので、30日以内にキャンセルすれば料金はかかりません。
火災報知器の電池の品番は、メーカーや機種によって違います。
取扱説明書や電池本体に記載されているので、購入前によく確認してくださいね。
以上のことから、火災報知器の電池は、家電量販店やホームセンターよりも、ネット通販で購入した方が楽で確実に手に入れることができるといえるでしょう。
火災報知器の電池交換は自分でできる
火災報知器の電池交換は、新しい電池があれば自分でできます。
ほかの道具は不要です。
やり方は、火災報知器を回して壁や天井から外し、コネクタを引き抜いて新しい電池と交換するだけ。
詳しくは後述しますが、電池の交換は難しく思えて実は簡単なのです。
私も実際に交換しましたが、簡単でした!
※ただし、配線式の火災報知器の取り外しの場合は電気工事士の資格が必要となり、この限りではありません
電気製品の電池切れは、突然やってきますよね。
火災報知器も例に漏れず、突然、音やランプによって電池切れのサインを示します。
火災報知器の電池切れ音は、メーカーや機種によってさまざま。
「電池切れです」や「ピッ…ピッ…ピッ…」などです。
こうなると、慌てて電器屋への依頼を思い浮かべてしまいがちです。
でもちょっと待ってください。
火災報知器は壁からの取り外しも、電池の交換も、自分でできてしまうのです。
火災報知器が電池切れした時の電池交換の費用
では、火災報知器の電池交換を自分でするといくらになるのか。
先ほど挙げた、パナソニックの火災警報器の交換用電池「SH384552520」を例にします。
我が家はAmazonで購入したのですが、2個で2000円しませんでした。
楽天市場で『SH384552520』を検索してみても、1個1000円前後で購入できることがわかりました(2023年7月現在)。
ヤフーショッピングでも同様です。
何個かセットでお得に販売しているお店もあります。
複数の部屋に火災報知器を設置しているご家庭は助かりますね。
ちなみに、賃貸のアパートなどでは、オーナーが費用を負担してくれる場合があります。
一度管理会社に確認してみると良いでしょう。
火災報知器の電池交換のやり方(外し方と付け方)
火災報知器の電池の外し方について、パナソニックの電池式住宅用火災警報器を例に解説します。
専用リチウム電池の外し方
1)火災報知器本体を取り外します
天井付けなら上に、壁付けなら壁の方に押しつけながら、半時計周りに回す(左に回す)と外れます。
2)電池を外します
専用リチウム電池から白と赤の線が出ていて、白いプラスチックのようなコネクタで繋がっています。
このコネクタを引き抜いて、電池を取り出しましょう。
この電池の型番をチェックして購入すればOKです。
新しい電池をセットする方法
1)コネクタをはめて、新しい電池を入れます
2)天井(または壁)に取り付けます
3)動作を確認しましょう
警報停止ボタンを押して「ピッ、正常です」となればOK!
参考:Panasonicよくあるご質問【住警器】住宅用火災警報器(電池式)の電池は交換できますか
想像よりずっと簡単に電池を外せると思いませんでしたか?
事実、電池交換はとても簡単です。
ただひとつ、電池交換で気をつけるべきことがあります。
交換後の動作確認です。
せっかく電池を入れ替えたのに、火災報知器がきちんと動作しなければ意味がありません。
万が一、有事が起こった際には命の危険も考えられます。
正しい手順に沿って電池の交換をしましょう。
火災報知器が電池切れで警告音がうるさい時の止め方(ピッ、など)
「電池切れの警告音がちょっとうるさすぎる!」
「新しい電池が手に入るまで鳴りっぱなしは困る!」
そんな人に向けて、先ほどのパナソニックの住宅用火災警報器を例に、うるさい電池切れ音の止め方を解説します。
警報を止めるには、警報停止ボタンを押す、または引き紐を引けばOKです。
ただし、電池切れのままの場合、単独型で16時間、ワイヤレス型で0~24時間以内に再び警報が鳴るそうです。
替えの電池を用意していない場合は、先ほどの外し方の要領で電池を抜くとよいでしょう。
我が家でも「ピッ・・・ピッ・・・ピッ・・・」と、大きな音ではないのですが、どこからか聞いたことがない音が鳴ってびっくりしたことがあります。
何の音かわからず、やっと火災報知器だと気づいたのですが、今度は消し方がわかりません・・・
というわけで、電池を抜いたら(コネクターを外したら)止まりました。
電池の外し方も、電池切れ音の止め方も簡単ですよね。
電池を外した場合は、音が鳴らないからと放置せず、安全のためにも電池は速やかに交換をしましょう。
また、メーカーや機種よっては警告音の違いがわかりづらく、実は故障のサインだった!なんてこともあります。
取扱説明書やメーカー公式サイト、で警告音の違いをよく確認しましょう。
さいごに
火災報知器の新築住宅への設置が2006年6月1日に義務化し、既存住宅への設置が2011年以降に義務化されました。
火災報知器の電池寿命は、およそ10年といわれています。
ご家庭にある火災報知器が気づかないうちに、実は電池切れをしている可能性はありませんか?
火災報知器は、自身や大切な人を火事から守るために欠かせないものです。
正しく管理して、みんなの安全を確保しましょう。
火災報知器は簡単に電池交換もできますが、10年を目安に本体交換が推奨されています。
我が家の電池は10年持たなかった気がしますが、電池切れの時は、本体の交換を検討するのが良いかもしれません。
買い替えの際は、このようなオーソドックスな形の火災報知器の他に、薄型や、家中の火災報知器が連動するようなタイプもあるので、お好みのものを選ぶとよいでしょう。